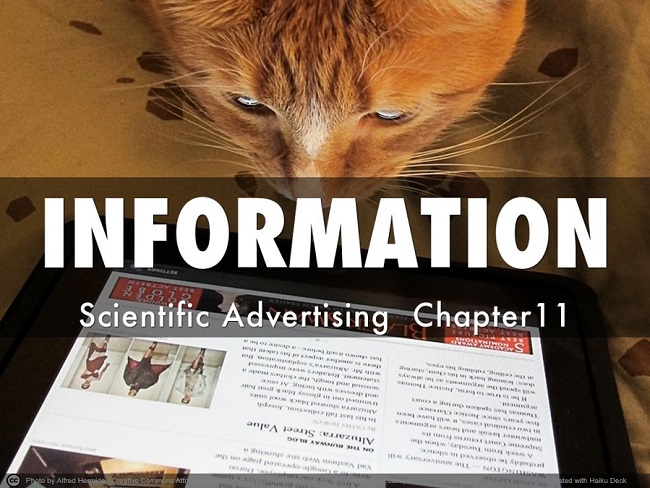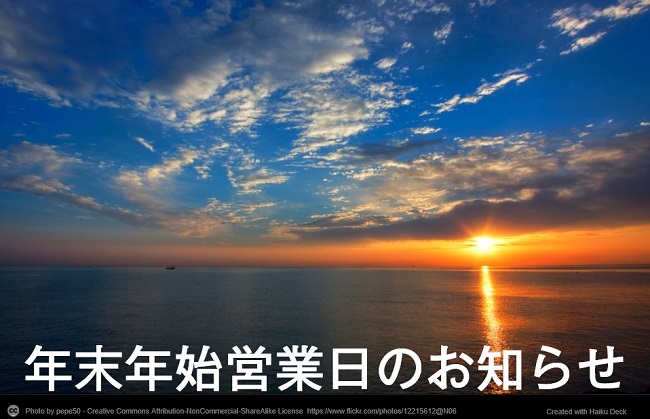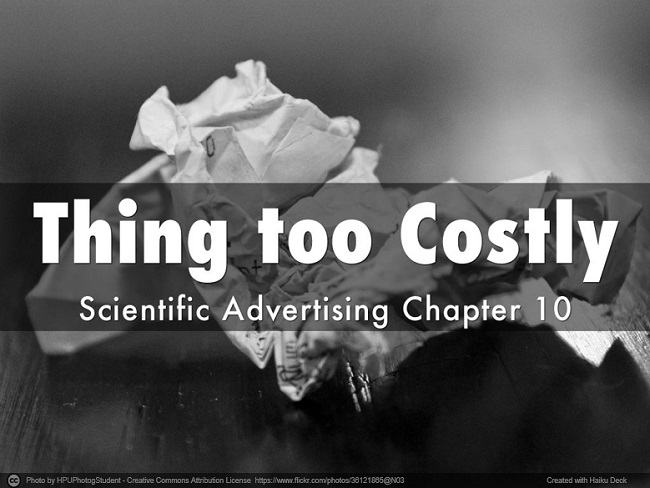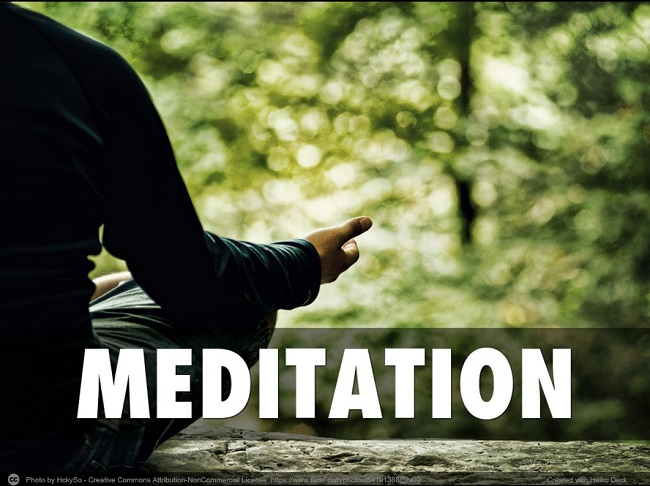世の中のマーケターが思い違いをしている致命的ポイント
広告の神様、デイヴィット・オグルヴィが称賛するクロード・ホプキンス氏は、
広告の文章は、短いコピーだけよりも、潜在顧客を納得させるだけの十分な材料(文章)が必要である と説いています。
(詳細は弊社Blogにて「なぜ、短いキャッチで製品は売れないか?広告で顧客を説得するためには!」)
Business Insider でそれを実証する記事「Why Short Advertising Copy Does NOT Sell More(なぜ広告の短いキャッチコピーで製品は売れないのか)」を見つけましたのでご紹介いたします!
マーケティングの大半は、リサーチと知識と正確なデータに基づいて行われています。
しかし、マーケティングを十分に勉強し、理解していないマーケターは、本人の意見や憶測を基に判断をしてしまう傾向があり、それは多くの思い違いを引き起こしています。
思い違いの代表例は、現代人は「簡潔なコピー(文章)を好んでいる」という点です。
その理由として、現代人は….
1、 文章を読むことを好まない
2、 限られた時間しか、文章に興味を持っていられない
3、 短い文章を読む習慣がついている
4、 溢れるメディアチャンネルに翻弄されている
5、 携帯やタブレットつい見てしまう習慣がある
確かに、現代人のこれらの傾向は間違っていない。
でも、これが理由で短いコピーのほうが売れるという結論には結びつきません。
全ては相対性理論である
優秀なマーケターとそうでないマーケターの違いはなにか。
それは、「どんな文章が長すぎるものであるのか、どんな文章が短いと感じるものであるのか」判断するのは、ターゲットである潜在顧客である、ということを知っているか知っていないか。
そこが決めてです。
ディカプリオ主演の、長編映画「タイタニック」を、10代の恋する女性が見れば、3時間を苦と思わずに見終えてしましょうでしょう。
人は不思議なもので、おもしろい!と思ったものに対しては、もっと知りたいという欲求を生み出します。
そして、興味がないと感じたものに関してはそれ以上知りたいだなんてもちろん思いません。
いいものに対しては、十分すぎると思うことはなく、そして、悪いと判断したものに対しては、すぐにお腹一杯と感じるものですね。
相対性理論を説いた、アルベルト・アインシュタインのTシャツにこう書いてあります。
「熱いストーブの上に座るとそれは一時間にも感じる苦痛な時間である。しかし、美しい女性が隣に座っている一時間はたったの一分であったかのような一瞬にも感じられてしまう。これこそが、相対性理論である」と。
「忙しく、怠慢」であるから簡潔さを求める
もちろん、コンテンツクリエイターでいる限り簡潔なキャッチコピーで潜在顧客に重要な情報を提供すべきです。
我々は忙しく、怠慢な生き物ですから。
簡潔であることは、
1)消費者の時間を節約することができる
2)忙しい消費者にも、あまり製品に興味を持たない消費者に対しても、明確なベネフィットを伝えることができる、
こんな素晴らしい利点がありますね。
しかし、簡潔なコピーに興味をもち、もっと読みたい潜在顧客がいたら?
そこが商品購入の重要なポイントである顧客のための情報はどう提供する?
優秀なマーケターは、盛り込みたい情報を「適当なサイズ(bite-sized=一口で食べれるサイズ)」に分けてフォーマットするのです。
たくさんの情報を求めていない潜在顧客は「写真」と「見出し」だけを見ればいい。
小見出しやそれ以上の情報は読まず、製品を購入するでしょう。
もっとたくさんの情報を求める潜在顧客は、広告内の全ての文章を熟読して、製品の品質や魅力を十分に理解して、納得した上で購入するでしょう。
「忙しくて怠慢な」潜在顧客でも全体の内容を熟読せずとも、何がベネフィットであるかを伝えられるようなフォーマットにすることです。
伝説のマーケター オグルヴィが世界のマーケターに伝えたいこと
オグリヴィは著書「Ogilvy on Advertising」でこういってます。
「素晴らしい多くの製品のマーケティングをしてきた経験から言えること。
それは、短いコピーよりも長いコピーのほうが、間違いなく製品が売れるということ。
長いコピーのある広告は、何が消費者にとってベネフィットであるかを印象付け、納得させることができるからである。
たとえ潜在顧客がそのコピーを読まなかったとしてもあることに意味がある。」
ニューヨーク大学リテイリング(小売経営)前学部長のチャールズ・エドワード教授もこう言っています。
「消費者に伝えたい事実が多いほど、製品は売れる。広告が成功する確率は、消費者に商品の適切な情報を伝えた量と比例する。」
John Caples氏は、彼の著書「Tested Advertising Methods」でこう言っています。
「ダイレクト・セールスに関わる広告主は、長いコピーを使った広告で結果を出している。
少ない単語やスローガンで構成される簡潔でリマインド形式のコピーは、製品・サービスに関する説明、そして消費者に提供するベネフィットを含んだ長いコピーと同じであるはずがないからである。」
もっとたくさんの専門家の引用をご覧になりたかったらこちら
http://www.businessinsider.com/using-the-power-of-three-to-your-marketing-advantage-2013-5
John Caples氏は学ぶことの多いマーケターでもあります。
彼についても今後ご紹介していく予定です。
現代のオンラインマーケットでも実証済
昔の知識人の引用ばかりで、それって現代にあてはまるのか?そう思っていませんか。
しかし、現代の有名マーケターは、100年以上前のクロード・ホプキンス氏の著書から広告の「超基本」を学んでいます。
過去の知識人の知恵を学ぶことはこれまでになく重要なことになってきています。
長いコピーが短いコピーよりも売れるという意実が、オンラインマーケティングでも実証され始めています。
Marketing Experiments社は、クライアント向けのテストを行い、長いコピーがウェブサイトのコンバージョン率を上げていることを実証しました。
全てのテストが、長いコピーがより優れた結果を出したことを証明したのです。
もっとたくさんの実例を知りたければ、Conversion Rate Experts社のウェブサイトを見てみてください。
彼らがどうやってCrazy Eggのコンバージョン率を363%まで上げることが出来たのか。
なんと、ただホームページのテキスト(文章)を20倍の長さにしたことがその理由です。
短いコピーよりも長いコピーが売れる理由
なぜ、短いコピーより長いコピーが売れるのか。
理由はたくさんありますが、7つに絞ってリストを作りました。
1、 消費者に、ベネフィットが何かを伝えることができる。そしてその一方、消費者も製品やサービス、企業について知ることができる。
2、 製品、サービス、企業を知らしめることは、それらの可能性を知らしめるチャンスである
3、 消費者の多くの疑問に答え、解決することができる
4、 多くの情報が欲しい消費者に対して情報を提供し、購買率を高めることができる
5、 多くのの情報を提供することは、消費者が安心して快適に製品を購入、また企業と取引を行うことができる
6、 「忙しく、怠慢」な消費者にも重要な情報な何であるかを提供することができる (良いレイアウトがされていることが条件であるが)
7、 重要なキーワードを含んだキャッチコピーはオーガニックサーチエンジンの検索率を高めることができる
広告の中で、文章情報がいかに重要であるか、ご納得いただけましたでしょうか?
世界の潜在顧客のなぜ?に答える、そして心をぐっとつかむキャッチコピーを発信しましょう。
引用元:
Business Insider
Why Short Advertising Copy Does NOT Sell More
http://www.businessinsider.com/if-you-think-short-copy-sells-more-think-again-2013-5#ixzz3Kj2xDCpn
We tell your story to the world!!